最近、ブログを読んでいて
「なんだか機械っぽいな」
「人間味がないな」
と感じること、ありませんか?
私自身、あるブログを読んでいたところ、「生成AIで作ったんだろうな」と何となく頭をよぎった瞬間、読むのをやめてしまったことがあります。
どんなに言ってることが正しくても、文章から“書き手の気持ち・人間性”が伝わらなければ、その文章を手に取ってくれる読者の心には届きません。
今は誰でも手軽にAIを使って文章が書くことができます。
だからこそ、
「この人の言葉選び素敵だな」
「この人のこと・考えをもっと知りたいな」
と思ってもらえることが、ブログの価値に直結するんですね。
自分が紡いだ言葉でも、AI判定ツールにかけると高い数値が出てしまうことも…
一体なぜ??
この記事では、
・AIっぽい文章になってしまう原因
・生成AI感を消すブログの書き方
について、具体的な例文を交えてわかりやすく解説していきます。
ある程度の文字数を書こうとしたときに、AIに頼ることがすべて悪なわけではありません。
むしろ使い方・使う部分によっては、文章作成するうえで強い味方になり得ます。
血が通った文章を書くために、どんなことに気を付けたら良いのか。
便利なAIと今後も上手く付き合っていくために、ぜひ参考にしてみてください。
AIっぽい記事は読まれない?
「生成AIっぽい記事」違和感の正体

何か調べ物をしているとき、偶然見つけたブログの記事を読んでいて、
「知りたい情報はまとまっているのに、なんだか読みにくい」
「文章は正しく書いてあるけれど、なぜか心に響かない」
など、“小さな違和感”を感じたことはありませんか?
それはもしかしたら“AIっぽさ”による違和感かもしれません。
生成AIの文章は、文法的には整っていて、誤字もなく、ぱっと見た第一印象は“当たり障りなくきれい”であることが多いです。
ですが、よくよく読み進めてみると、「あれ…なんか変だぞ?」と読み手が違和感を感じてしまうポイントがいくつかあります。
具体的な例を挙げてみると、
・同じような言い回しや表現を繰り返す
→特定のプロンプトを使いまわしている方は分かると思いますが、文の出だしや言い回しが、特定の文言・語尾で終わることが多くありませんか?
・文法は教科書通り、でもなぜか“冷たい”
→言葉の“遊び”がない。
・経験や感情がなく、事実だけを並べている印象
→「○○してしまった」「○○できて嬉しい」といった感情を表す単語が極端に少ない。
インターネット上の情報を集約しているに過ぎないため、事実を補足する(裏付ける)経験談がなく、内容が薄っぺらくなりがち。
・会話文やツッコミがなく、淡々としている
→その人特有の句読点の使い方、「“”」や「…」などを用いた言葉の“間”がない。
などの特徴があります。
教科書通りの文法で作られた当たり障りのない文章は、一見まとまっていて綺麗に見える一方で、やはり「人間の言葉」ではないと感じてしまうのです。
これが“AIっぽさ”の違和感の正体なのです。
“誰でも欠ける文章”はAIが書いてくれる。
だからこそ、“誰かが書いた”ブログの価値は、「その人の体験」や「その人の考え方・人間性」を感じられるかどうかが大きく影響するんです。
「これはAIが書いたっぽいな」と感じた瞬間に、読者との距離が一気に開いてしまうのはそのため。
構成や見出し・文章流れを考えるのにAIの力を使うのはとても便利ですが、最後に“人の言葉”として整えることが、欠かせない作業になるんです。
次の項目では、この“AIっぽい”と感じる違和感をどうやって払拭していくのか、具体的にできる工夫をご紹介していきます。
読者が離脱する3つの典型パターン
表面的な情報ばかりで深掘りがない
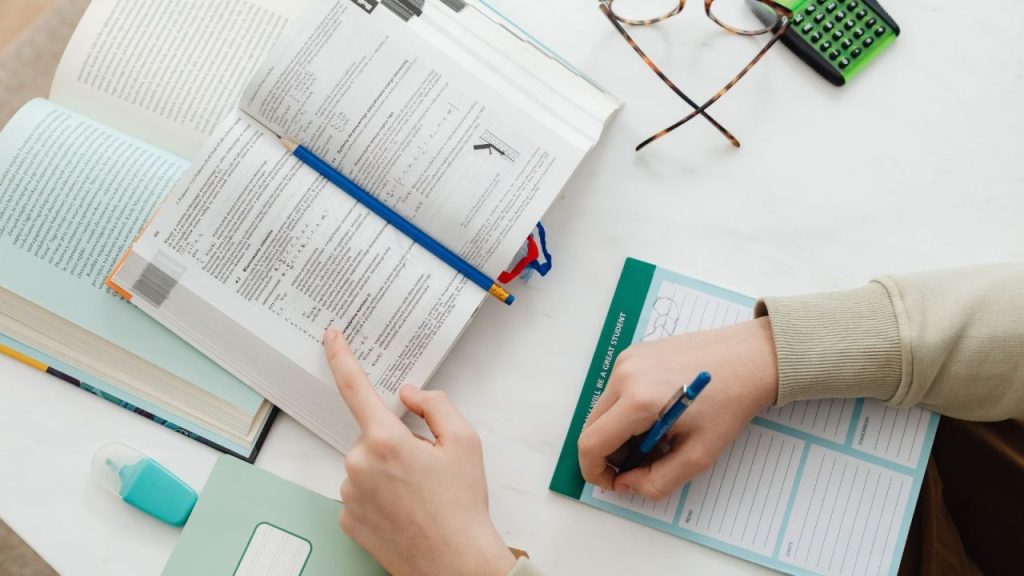
AIはインターネット上の情報をベースに文章を作るため、どうしても誰でも知っている一般論になりがち。
ですが、「それ、知ってるよ」「どこかで見たことあるなあ」と思われてしまった時点で、読者の関心は薄れていき、そのまま離脱していきます。
読み手が求めているのは、“あなたにしか書けない感情のこもった文章”。
自分の考えや具体的な体験談、経験を通して気づいたことなどの主観的要素を積極的に取り入れていきましょう。
・「自分はこう思う」という考えを構成に盛り込もう。
・(もしあれば)失敗談、こうしたら成功した、などの経験談を積極的に公開しよう。
感情が伝わらない
AIの文章は、語尾が丁寧すぎたり(やたらと「です」「ます」/体言止めを使用しない)、感情表現が控えめだったりすることが多くあります。
すると、「書き手の熱量」が伝わらない=読み手が「共感」しづらくなる。
ブログは“人(書き手)が人(読み手)に話しかける”メディアです。
正確な情報を伝えることはもちろん、それに付随する「“誰か”の意見や実体験」も同時に求められています。
事実を知るだけでいいなら、それこそAIに聞くなり、インターネットで調べれば十分!
書き手の感情が伝わらなければ、いくら内容が正しいものでも文章はどこか味気なく無機質に感じられてしまうのです。
・文章や言葉選びの中に自分の感情を盛り込もう。
・語尾や言い回しのバリエーションを増やして、文章に緩急をつけよう。
・読み手の共感を得るために、プロンプトに「読み手の対象はどんな人物なのか」を必ず含めよう。
文章に“引っかかり”がない
生成AIが生み出す文章には、「誤字脱字がない」「独特の言い回しは好まず、一般的な言い回しを繰り返し使う」という特徴があります。
まるで教科書のお手本のようなスムーズな日本語・文書を作成できることが強みですが、それが裏目に出て、サラ~ッと読み流されやすい=印象に残らないという弱点にもなり得ます。
ときには、読者に対して疑問を投げかけてみたり、文中に話し言葉を交えたりすることで、文章の流れを変える・読者の注意を引きつける「ひっかかり」が生まれます。
これがあると、自然と“読者がスクロールを止める”んです。
どれも「書いている側」は気づきにくいポイントですが、読者の立場で見れば“読む理由がない文章”になってしまっているんですよね。
2024年以降に行われたGoogleのアップデートでは、「役に立たない生成コンテンツ」の順位が下がったという報告も。
つまり、「AIっぽさ」は、読者だけでなく検索エンジンからもマイナス評価を受ける可能性があるというわけ。
こういった“AI感”を減らすためにはどうしたらよいのか。
以下では、実際に私が意識していることや、具体的な工夫をご紹介していきます。
AIっぽさを感じさせないためにやるべきこと
体験・感情・具体性を盛り込む

「この人の話おもしろいな!」
「どんな人なのか知りたい、もっと読んでみたい」
そう思わせる文章には、必ず“その人にしかできない表現・書けない言葉”が含まれています。
その言葉を生み出すのに必要なのが、ズバリ 体験・感情・具体性という3つの要素。
この3つを意識して文章に加えるだけで、AIっぽさを感じさせる違和感は一気に薄れていきます。
たとえば、ただ「ブログ記事はリライトが大事です」と書くよりも、
私自身、3年前に書いた記事をリライトしただけで検索順位が20位→3位にぐっと上がったことがあります。
その時初めて「リライトってこんなに効果があるのか!」とすごく驚きました。
と書いた方が、読み手に印象が残りやすいですね。
ポイントは、「◯年前」「◯位」といった具体的な数字を示すこと、「ぐっと」「リライトって…」など、擬音や自分がその時感じたことを加筆すること💡
このように、自分の実体験やそのときの気持ちをセットで伝えると、文章がぐっと人間らしくなり、読者の共感を得られやすくなります◎
生成AIの文章は、どうしても浅い一般論で、誰からも反感を買いづらい“中立的な立場に置かれた回答”になりやすいもの。
そこに自分自身の体験・気持ち・具体例を足すだけで、読者にとっての“読む価値”が大きくアップするのです💪
テンプレ文・ありきたり表現を避ける
ブログを書くとき、つい「文頭・文末で同じ言い回しを使用する」「特定の言葉を多用する」ことがあると思います。
実際に記事を書く時に、ある程度構成を定型化しておくことは、効率アップの為に有効ですよね。
しかし、実はそれがAIっぽさを感じさせる大きな原因になっていることがあります。
自分で書いた文章なのに、AI判定ツールで高い数値が出てしまう、という方は似たような表現・言葉・語尾を多用していないか、改めてチェックを!
記事の構成は定型化したとしても、文章自体をコピーするのではなく、様々な言い回し・言い換えのバリエーションを持ち、自分自身の言葉で伝えていく努力が必要です。
句読点・改行・語尾で“人らしさ”を出す
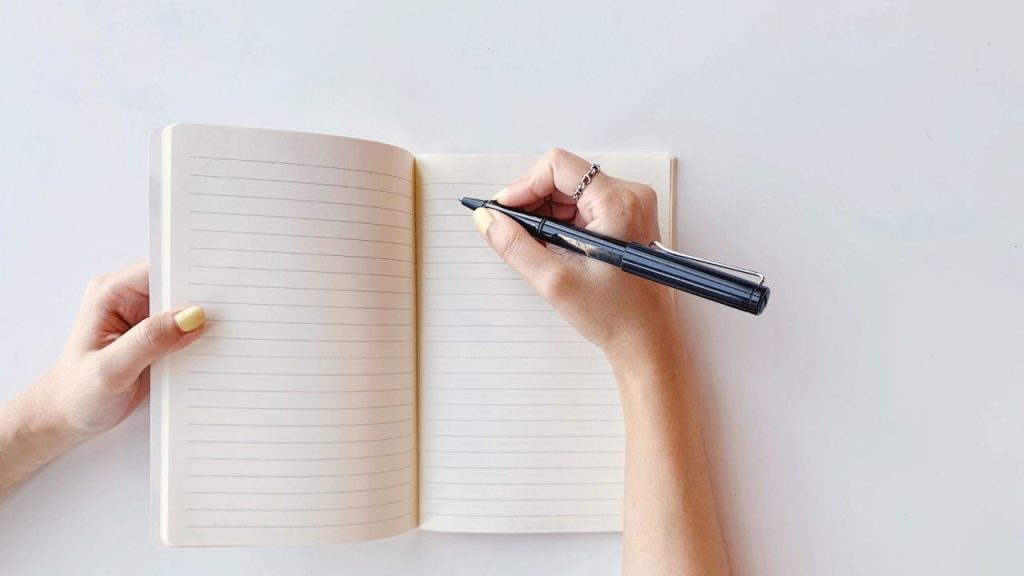
文章の印象は、言葉の内容だけでなく、句読点の使い方や改行のタイミング、語尾の表現でも大きく変わります。
たとえば誰かが書いた文章を読んだとき、「これは自分(もしくは近しい誰か)が書いた文章じゃないな」と、直感的に分かる場合がありますね。
それは、“その人独自の言葉の区切りやリズム、語尾の好み”があるから。
だから「自分(あの人)はこういう書き方しないよな」とすぐにわかるのです。
一方でAIが作る文章は、文法的に正しくぱっと見はキレイに整っている反面、どうしても“味気なく無機質なリズム”になりがちです。
そこで、もしAI生成した文章の原案を利用する場合には、
語尾の部分だけでも自分らしい「話し言葉」や「間の取り方」に変えてみる
ことをおすすめします。
具体的には、
・「、」や「。」の使い方をあえて少し崩してみる
→「、、」や「。。」などの二重使い、「・」での代替
・長い文章は適度に改行して読みやすくする
→AI生成した文章は、流れるように読める一方一文が長くなりがち。
適度なところで自分で区切り、語尾をアレンジする。
・「〜ですね」「〜と思います」「〜かもしれません」など語尾で柔らかさや親近感を出す
ちょっとしたことですが、こうした細かい工夫・手間をかけていくことで、読者に「人が書いている」と感じてもらえるようになります。
ような文章”に仕上げることが大切です。
ぜひ、自分の声を思い浮かべながら書いてみてくださいね。
まとめ:AIの力を借りつつ“人間らしさ”を添える
生成AIは、まず何といっても非常に便利。
効率よく文章の骨組みを作ったり、アイデアを整理したりするのにとても役立ちますよね。
実際に私も、ブログで記事を書く時には、記事の構成や見出しの作成をAIに手伝ってもらうことがよくあります。
だって、私が一から考えるよりもずっと上手く、読み手の悩みや意図を組んだ内容を抽出してくれるから。
しかし、その便利さに全面的に甘えて頼り切ってはいけません。
大切なのは、AIが作った構成・見出し・文章に“自分らしさ”や“血が通った言葉の温かみ”を加える手間を惜しまないことです。
AIやインターネットでいくらでも情報収集が可能なこの時代、読者は正確な情報だけでなく、「実体験を聞きたい」「自分以外の誰かが紡ぐ言葉を読みたい」と思って、わざわざあなたのブログを訪れるのです。
ここまで詳しく解説してきた通り、生成AIの便利な力を借りつつも、
・自分の体験や感情を盛り込む
・自然な話し言葉やリズムを意識してみる
・特定の表現の繰り返しを避け、自分の言葉を紡ぐ
ことが大切です。
AIはあくまでも生活を便利にするお助けツール。
どんなに便利で、学習能力が高くて賢くても、人に替わることはできません。
最終的に読者の心に届くのは、同じ人間である“誰かが紡いだ言葉”です。
AIと人間、それぞれの強みを活かして、魅力あるブログ運営を継続して発信していきたいですね!

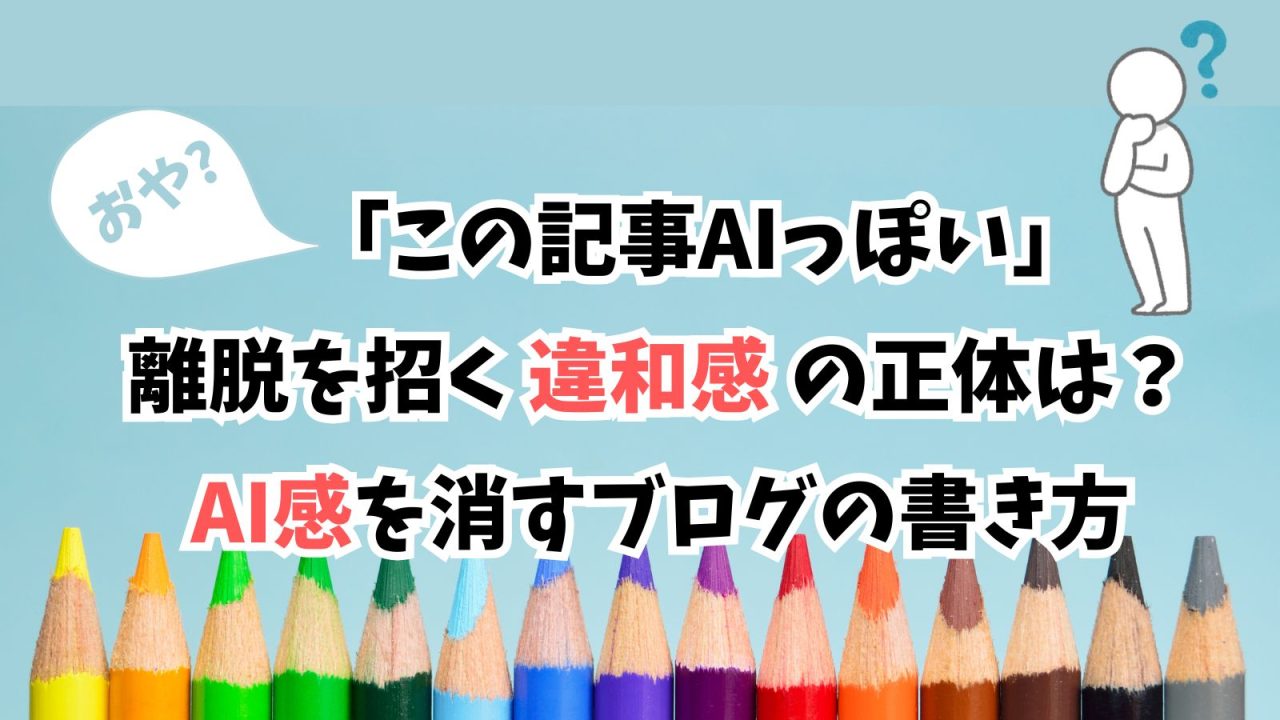

コメント